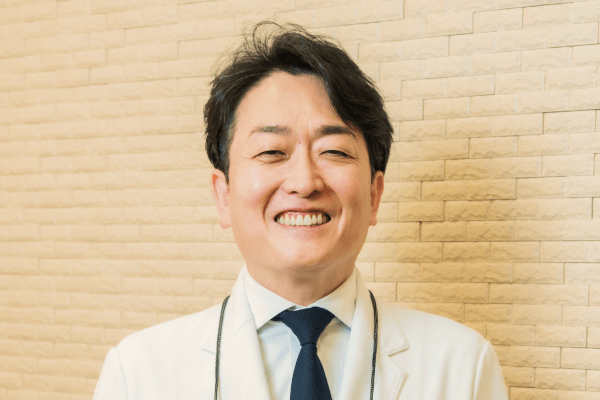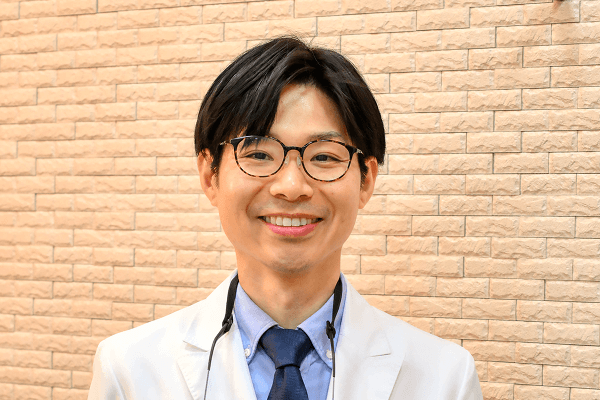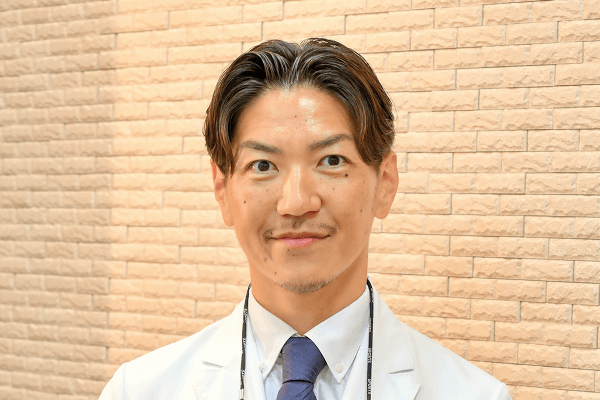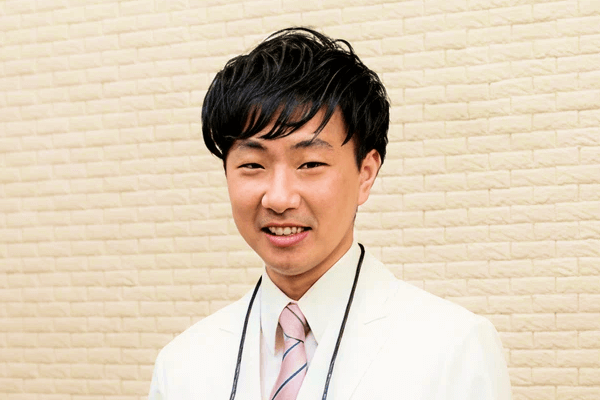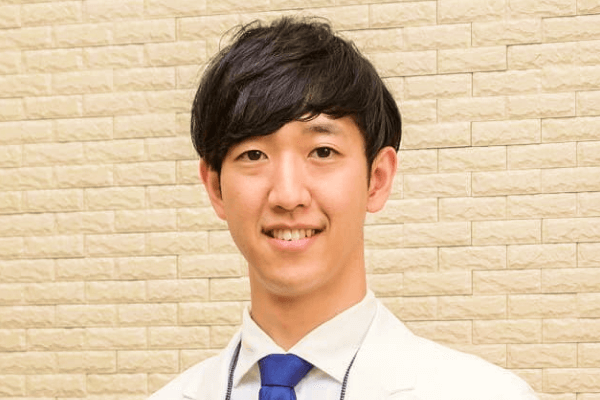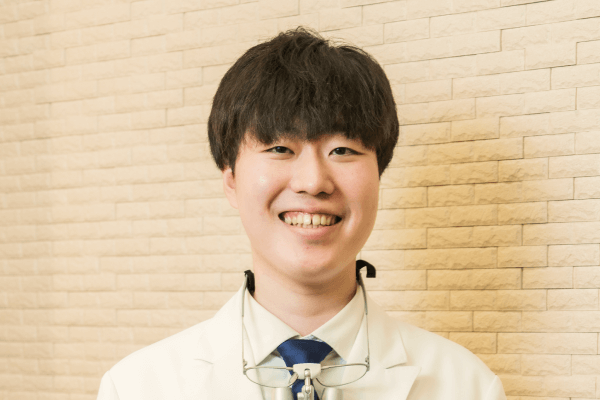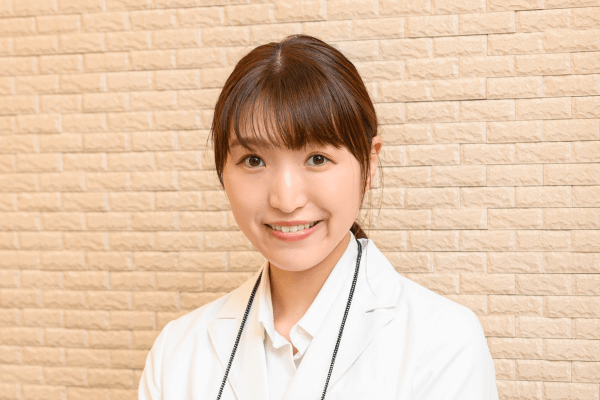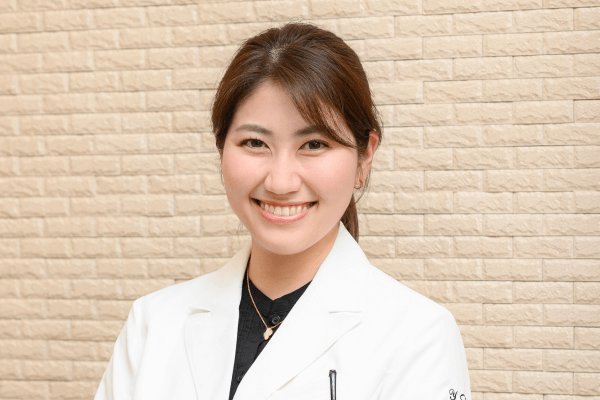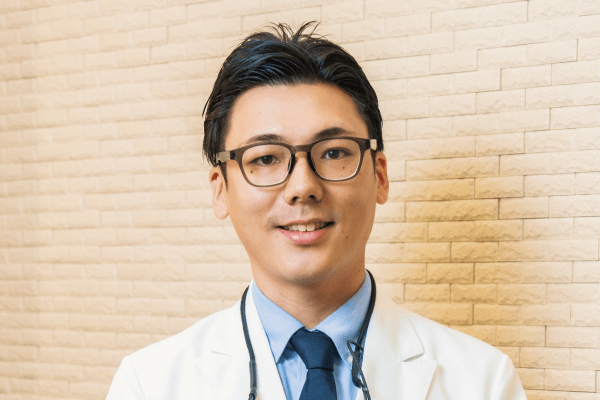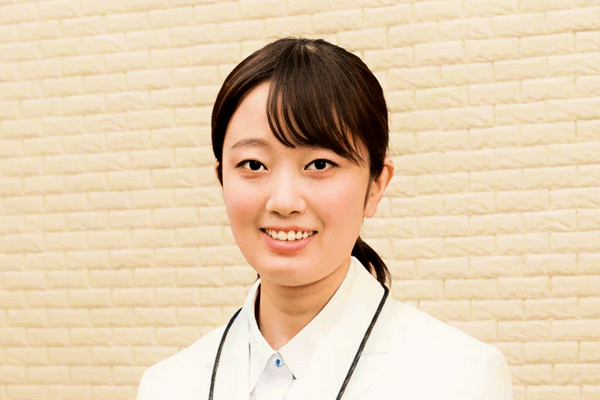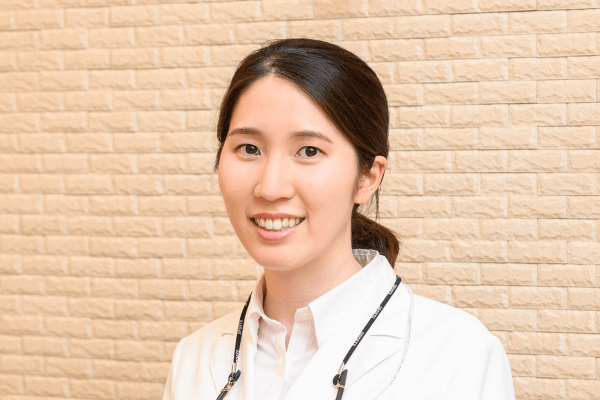「最近、歯を食いしばっていることが多くて歯が痛い…」「朝起きると顎が疲れているけど大丈夫かな…」と心配な方も多いのではないでしょうか。
食いしばりは多くの人が経験する症状ですが、放置すると歯や顎に深刻な影響を与える可能性があります。
食いしばりは適切な対処法を知ることで改善できる症状でもあるため、現在お悩みの方はもちろん、予防したい方も武蔵小杉パークシティ歯科医院へお気軽にご相談ください。
食いしばりとは?

食いしばりは、上下の歯を強く噛み締める癖のことで、医学的には「ブラキシズム(歯ぎしり・食いしばりなどの総称)」の一種です。
多くの場合、本人が気づかないうちに日常生活や睡眠中に行われています。
通常、リラックス時には上下の歯の間に2〜3mmの隙間がありますが、ストレスや緊張状態になると無意識に歯を接触させてしまい、咀嚼筋が過度に緊張します。
仕事中のパソコン作業や運転時など集中しているとき、あるいは睡眠中にも食いしばりは起こります。自覚しにくいため、歯の摩耗や顎の不調が進んでから気づくケースも少なくありません。
食いしばりと歯ぎしりの違い
食いしばりと歯ぎしりは混同されやすいですが、異なる特徴があります。
- 食いしばり
歯を強く噛みしめ続ける。音が出にくい。 - 歯ぎしり
歯を横方向にこすり合わせる。「ギリギリ」という音がする。
「夜中に音がしないから安心」と思われがちですが、実は食いしばりの方が持続的に強い力がかかるため、歯の破折や顎関節症につながりやすいとされています。
どちらも無意識に起こりやすく、家族からの指摘や歯科検診で初めて発見されることも多いため、早期発見と対処が重要です。
食いしばりの原因

食いしばりは単なる癖ではなく、いくつかの要因が重なって起こる症状です。
主な原因としては、精神的ストレス・噛み合わせの問題・生活習慣の乱れが挙げられます。これらの影響により、歯や顎の筋肉に過度な負担がかかることがあります。
特に多いのはストレスによるものです。仕事や人間関係の緊張が無意識のうちに筋肉を収縮させ、歯を強く噛みしめる動作につながります。
また、歯並びや噛み合わせの不調も要因のひとつで、不自然な咬合状態が筋肉の緊張を誘発します。具体的には、パソコン作業中の集中時や運転中、さらには睡眠中に無意識に行われることが多く、朝起きたときの顎の疲労感や頭痛として現れることがあります。
放置すると歯の摩耗や顎関節の不調、肩や首のこりにつながることもあるため、早めの対策が大切です。
食いしばりの種類と特徴

食いしばりにはいくつかのパターンがあり、それぞれ特徴が異なります。
自分の症状を知ることは、適切な対処法を見つける第一歩になります。
クレンチング(持続的な噛みしめ)
上下の歯を強く噛み締めるタイプで、音が出ないのが特徴です。
睡眠中だけでなく、日中の仕事や勉強の集中時にも無意識に行われやすい傾向があります。
主な症状は以下の通りです。
- 朝起きたときの顎の疲労感や痛み
- 奥歯や犬歯の摩耗や欠け
- 頬の内側に歯型の跡がつく
- 舌の縁にギザギザした跡が残る
- 首や肩のこり、頭痛
「最近、朝に顎が重たい」「歯が欠けやすい」といったサインがある場合、クレンチングの可能性があります。
タッピング(カチカチと噛み合わせる動き)
上下の歯を小刻みに接触させるタイプで、カチカチという音が出やすいのが特徴です。
日中の緊張や集中時に起こることが多く、無意識に繰り返されます。
主な症状は以下の通りです。
- 歯の接触音が周囲に聞こえる
- 顎の筋肉が疲れる
- 歯の表面が徐々に摩耗する
- 顎関節に違和感や痛みが出る
放置すると歯や顎への負担が積み重なり、顎関節症のリスクも高まります。
グラインディング(横にこする動き)
主に睡眠中に見られ、上下の歯を横方向にこすり合わせるタイプです。
一般的には「歯ぎしり」と呼ばれる動作で、大きな音を伴うことが多く、家族から指摘されて気づくケースもあります。
歯の摩耗や欠けにつながるため注意が必要ですが、詳しくは「歯ぎしりページ」をご覧ください。
食いしばりは音が出ないケースも多く、自分では気づきにくい特徴があります。気になる症状がある場合は、歯科医院でのチェックをおすすめします。
咬合性外傷について
強い食いしばりが続くと、歯や歯ぐきに過度な力がかかり「咬合性外傷」と呼ばれる状態になることがあります。
例えば、下記のような症状がサインになることもあります。
- 特定の歯だけがしみる・痛む
- 歯がぐらつくように感じる
- 噛んだとき違和感がある
詳しくは、歯ぎしりページの「咬合性外傷」をご覧ください。
食いしばりの治療法

食いしばりの治療は、症状の程度や原因に合わせて方法を選ぶことが大切です。
早めに対処することで、歯や顎への負担を減らし、症状の悪化を防ぐことにつながります。放っておくと、歯の摩耗や欠け、顎関節の不調、肩こりや頭痛など全身の不調に広がることもあります。
安心して生活できるように、総合的に取り組んでいくことが大切です。
主な治療法には、下記があります。
- マウスピースで歯を守る方法
- 噛み合わせを整える治療
- ストレスケアや生活習慣の改善
特にマウスピースは、すぐに始められて多くの方が効果を実感できる治療です。
マウスピースの効果と使用法
マウスピースは、夜間の無意識な食いしばりから歯を守る基本的な治療です。
歯科医院で作るオーダーメイドタイプなので、自分の歯にぴったり合い、安心して使えます。
マウスピースの主な効果
- 歯の摩耗や欠けを防ぐ
- 顎関節への負担をやわらげる
- 筋肉の緊張を緩め、頭痛や肩こりの改善につながる
- 睡眠の質を高める
基本的には就寝時に装着します。初めは違和感を感じる方もいますが、1〜2週間ほどで慣れることがほとんどです。
日中も食いしばりが強い方には、薄型のマウスピースを使う方法もあります。定期的な調整を行えば、長く効果を維持できます。
矯正治療の役割
食いしばりは、まずマウスピースで歯を守るのが基本です。
ただし、噛み合わせに問題がある場合には、矯正治療や被せ物の調整などで噛み合わせを整えることがサポートになります。
歯並びや噛み合わせが乱れていると、特定の歯や顎に力が集中してしまいます。矯正によって力のかかり方を分散できれば、歯や顎への負担をやわらげることが可能です。
矯正は「食いしばりを直接なくす治療」ではありませんが、症状の悪化を防ぎ、口全体を守るための手段のひとつになります。
ストレス管理とリラクゼーション
食いしばりの大きな原因のひとつがストレスです。
気づかないうちに筋肉が緊張し、強い噛みしめにつながってしまいます。
そのため、ストレスを和らげる工夫やリラックスできる習慣も大切です。
食いしばりに関するよくある質問
食いしばりは、日中のくせや夜間の無意識の動きとして起こることが多く、気づかないうちに歯や顎に負担をかけてしまいます。
そのため、「自分は食いしばりをしているのかな?」「どんな治療が必要なのだろう?」と不安を感じる方も少なくありません。ここでは、患者さんから寄せられることの多いご質問をまとめました。
食いしばりについて正しく知ることで、早めに適切なケアを始めるきっかけにしていただければと思います。