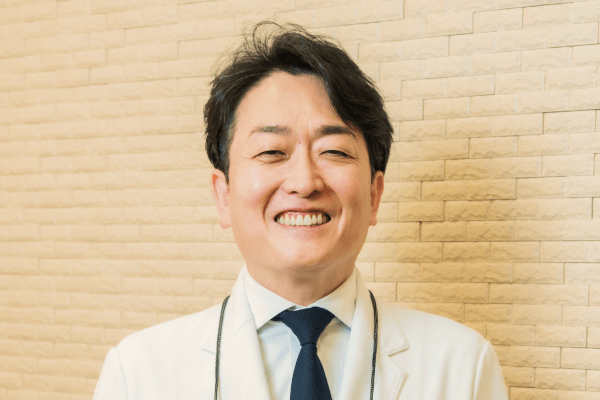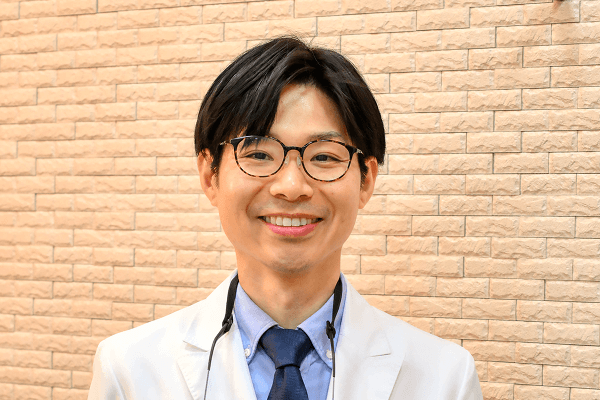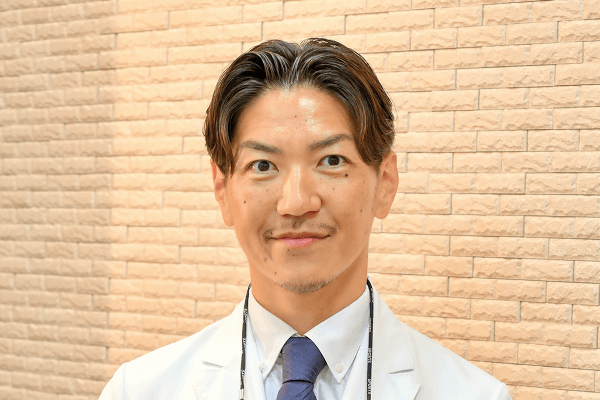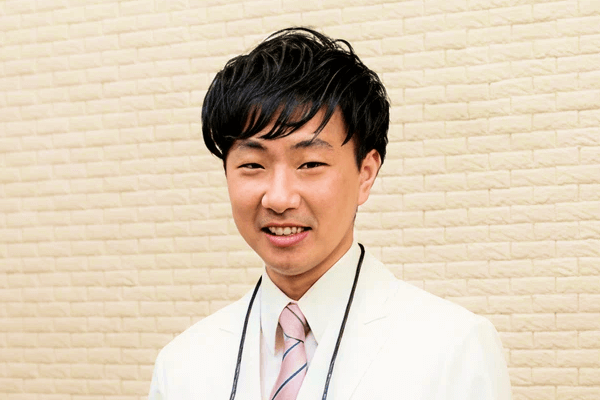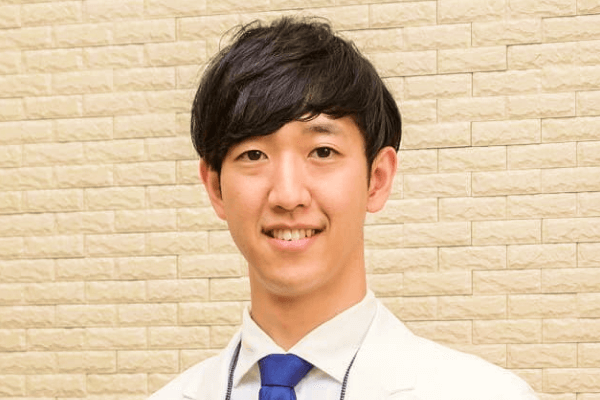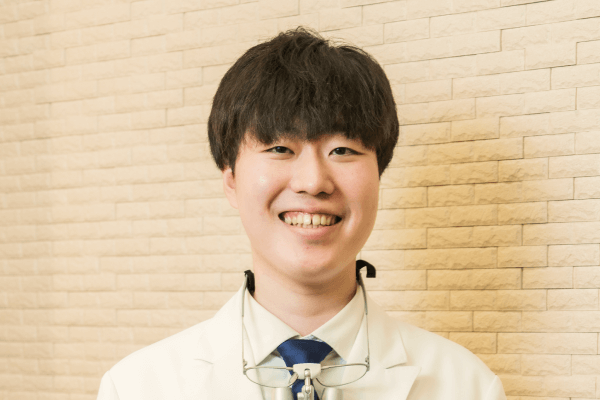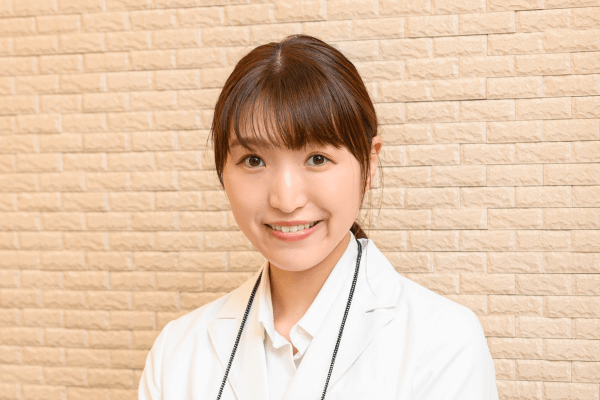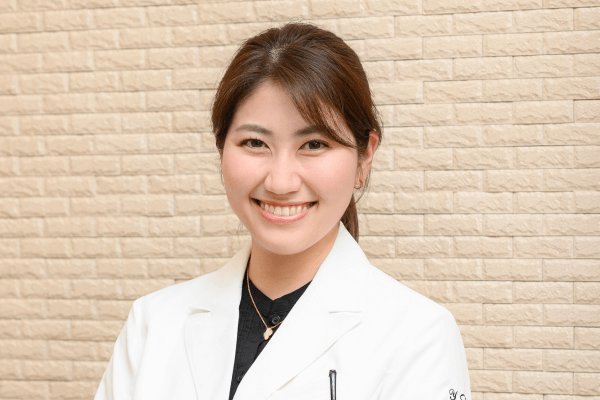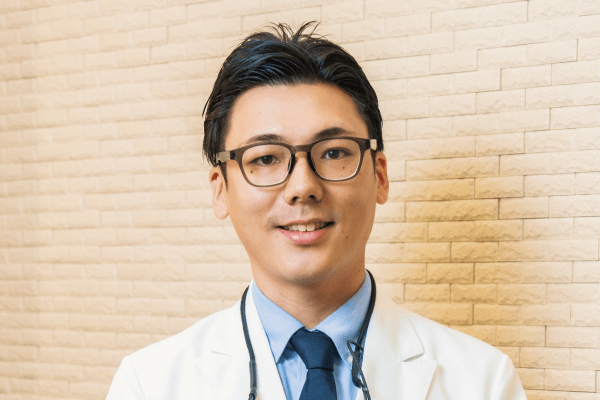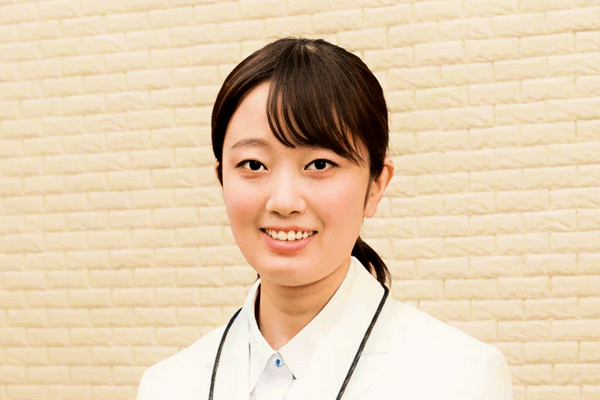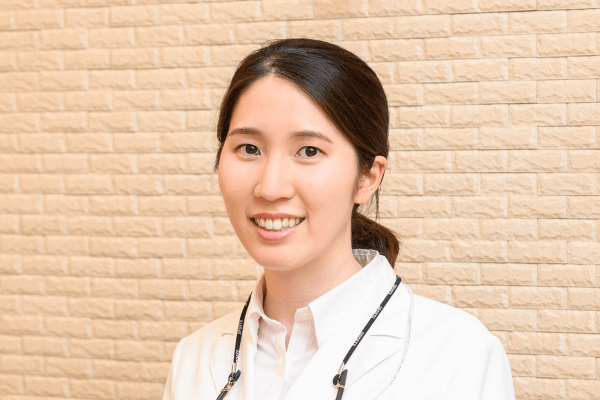「夜中に歯ぎしりをしているって言われたけど大丈夫かな…」「朝起きると顎が痛いのは歯ぎしりが原因かもしれない…」そんな心配を抱えている方は少なくありません。
歯ぎしりは放置すると歯や顎に深刻な影響を与える可能性があるため、早めの対処が重要です。
歯ぎしりは適切な知識と対策があれば改善できる症状です。歯ぎしりでお悩みの方はぜひ参考にしてください。
歯ぎしりとは

歯ぎしりは、睡眠中や日中に無意識に歯を強く噛み合わせたり、こすり合わせたりする行為です。
医学的には「ブラキシズム」と呼ばれ、多くの人が経験する一般的な現象です。
この現象が起こる背景には、ストレスや緊張、噛み合わせの異常、遺伝的要因など複数の原因が関係しています。現代社会では特にストレスが大きな要因となっており、仕事や人間関係の悩みが歯ぎしりを引き起こすケースが増加中です。
例えば、重要なプレゼンテーションを控えた夜や、人間関係でトラブルを抱えているときに歯ぎしりが強くなる傾向があります。
また、カフェインの過剰摂取や喫煙、アルコールの影響も歯ぎしりを悪化させる要因として知られています。
歯ぎしりの原因

歯ぎしりの原因は複数の要因が複雑に絡み合って発生します。最も大きな要因は、ストレスや精神的な緊張です。
現代社会では「仕事のプレッシャーが強くて夜も気が休まらない…」と感じる方も多いはずです。このような心理的ストレスが睡眠中の歯ぎしりを引き起こす主要な原因となっています。
身体的な要因も見逃せません。
- 噛み合わせの異常や歯並びの問題
- 顎関節症などの顎の機能障害
- 睡眠時無呼吸症候群との関連性
- アルコールやカフェインの過剰摂取
- 特定の薬物の副作用
遺伝的要素も関係しており、家族に歯ぎしりをする人がいる場合は発症リスクが高まります。また、睡眠の質の低下や不規則な生活リズムも歯ぎしりを悪化させる要因です。
年齢や性別による違いもあり、成人では女性の方がやや多い傾向にあります。
これらの原因を理解することで、適切な対策を立てることが可能になります。
歯ぎしりの種類

歯ぎしりは、その動作の特徴によって大きく3つのタイプに分類されます。
- グラインディング:歯の表面が削れやすい
- クレンチング:顎の筋肉に強い負担をかける
- タッピング:歯の先端部分に集中的な力が加わる
それぞれの種類を理解することで、自分の症状に適した対策を講じることができます。
グラインディング:歯をこするタイプ
グラインディングは歯ぎしりの中で最も一般的なタイプで、上下の歯を横方向にこすり合わせる動作を指します。
睡眠中に無意識に行われることが多く、「ギリギリ」という特徴的な音が発生するため、家族から指摘されて気づく方も多くいらっしゃいます。
この動作は主に睡眠の浅い段階で起こりやすく、ストレスや緊張状態が続くと頻度が増加する傾向があります。
「最近よく眠れていない気がする…」と感じている方は、グラインディングが原因で睡眠の質が低下している可能性も考えられます。
グラインディングの特徴は以下の通りです。
- 歯の表面が平らに削れる咬耗が起こりやすい
- エナメル質の摩耗により歯が短くなる
- 顎の筋肉に過度な負担がかかり朝の疲労感につながる
- 歯の神経が露出して知覚過敏を引き起こすリスクがある
放置すると歯の寿命を大幅に短縮させる恐れがあるため、早期の対策が重要です。
タッピング:歯を打ち合わせるタイプ
タッピングは歯ぎしりの中でも比較的珍しいタイプで、上下の歯を小刻みに打ち合わせる動作を繰り返します。
「カチカチと音がしているかもしれない…」と家族から指摘されることも多いかもしれません。
この症状は主に浅い眠りの時に発生し、歯同士が接触する際に特徴的な音を立てます。グラインディングのような擦る動作とは異なり、歯を上下に動かして接触させる動作が中心となります。
タッピングの主な特徴は以下の通りです。
- 歯を打ち合わせる際の「カチカチ」という音
- 浅い眠りの段階で発生しやすい
- 他の歯ぎしりタイプと比べて歯への負担は軽い
- 音により同居者の睡眠を妨げる可能性
ただし、音が小さい場合は本人も周囲も気づきにくく、発見が遅れることがあります。朝起きた時の顎の疲労感や違和感で初めて気づく方も少なくありません。
タッピングは他のタイプと併発することもあるため、総合的な観察が重要となります。
咬合性外傷とは
歯ぎしりや食いしばりが続くと、歯や歯ぐきに過度な力がかかり「咬合性外傷」という状態を引き起こすことがあります。
これは歯周病のように細菌が原因ではなく、過剰な力が原因で歯や歯周組織が傷つく状態です。
主な症状には以下があります。
- 歯が揺れる
- 噛むと痛い
- 歯ぐきに違和感や腫れがある
- 特定の歯に過度な力が集中する
放置すると歯周組織が破壊され、最悪の場合は歯を失うことにつながります。
歯周病と混同されやすい症状ですが、原因は「細菌」ではなく「力」である点が大きな違いです。
気になる症状がある場合は、早めに歯科医院で診断を受けることが大切です。
歯ぎしりの治療法

歯ぎしりの治療は、症状の程度や原因に応じて適切な方法を選択することが重要です。
歯を直接守る方法と生活習慣の改善を組み合わせることで、症状の軽減と再発防止の両方が期待できます。
マウスピースの使用と効果
マウスピース(ナイトガード)は、歯ぎしりによる摩耗や破折から歯を守る最も実用的で効果の高い治療法のひとつです。
睡眠中に装着することで歯同士の接触を防ぎ、顎の筋肉の緊張も和らぎます。
その結果、朝の顎の疲労感や頭痛が軽減されることもあります。
武蔵小杉パークシティ歯科医院では、一人ひとりの咬み合わせに合わせてオーダーメイドのマウスピースを作製しています。
快適に使用できるため、長期的に歯を守る習慣として取り入れやすい治療法です。
ストレス管理と生活習慣の見直し
歯ぎしりの大きな要因のひとつは、ストレスや生活習慣の乱れです。
そのため、以下のような取り組みも有効とされています。
- 就寝前の深呼吸やストレッチによるリラックス
- 適度な運動や趣味によるストレス解消
- カフェインやアルコールを控える(特に就寝前)
- 規則正しい生活と十分な睡眠の確保
これらは症状を和らげる一助になりますが、歯を直接守るにはマウスピースの使用が最も効果的です。
武蔵小杉パークシティ歯科医院での専門的な治療と対応

歯ぎしりや咬合性外傷は、自覚しにくく進行してから気づくケースも多い症状です。
武蔵小杉パークシティ歯科医院では、歯や顎関節の状態を丁寧に検査し、症状に応じた治療を行っています。
当院で行っている主な治療は、下記を組み合わせることで、歯や顎へのダメージを最小限に抑えます。
- マウスピース(ナイトガード)の作製
- 咬み合わせの調整
- 補綴治療による歯の負担軽減
多くの患者さんが数か月で症状の改善を実感されており、早めの受診が効果的です。
歯ぎしりに関するよくある質問
歯ぎしりは自分では気づきにくいため、不安や疑問を抱える方が少なくありません。
ここでは、患者さんから特によく寄せられる質問をまとめました。
正しい知識を知ることで、早めの対策や治療につなげることができます。
- 寝ているときの歯ぎしりは、治せますか?
-
完全にやめるのは難しいですが、マウスピースで歯を守りつつ、生活習慣やストレス対策で軽減できます。
- マウスピースが壊れてしまいました。どうすればいいですか?
-
耐久性のある素材に作り直すのがおすすめです。
日中の食いしばりにも注意し、早めに歯科で相談してください。
- 歯ぎしりは、完治しますか?
-
「完治」よりも「症状のコントロール」が現実的です。
マウスピース・睡眠改善・ストレス管理で軽くなるケースが多いです。
- 歯が欠けました。放置しても大丈夫ですか?
-
放置すると欠けが広がったり知覚過敏になることがあります。
早めに歯科でチェックしてもらいましょう。
- 歯ぎしりで、マウスピース以外の対策はありますか?
-
顎の力を抜く習慣やストレス対策、睡眠改善などが有効です。
ただし、歯を守るにはマウスピースが最も確実です。
子どもの歯ぎしりに関するよくある質問
- 子どもの歯ぎしりは、病気ですか?
-
多くは乳歯から永久歯に生え変わる時期に見られる一時的な現象です。
すぐに心配はいりません。
- 子どもの歯ぎしりは、いつまで様子を見て大丈夫?
-
永久歯が生え揃う12歳前後で、自然に落ち着くことが多いです。
ただし歯が欠ける・摩耗が強い場合は早めに相談してください。
- 子どもの歯ぎしりは、治療が必要ですか?
-
軽度であれば、経過観察で十分です。
必要に応じて、子ども用マウスピースを作ることもあります。
- 子どもの歯ぎしりは、ストレスが原因でなることもありますか?
-
はい。環境の変化や学校での出来事が影響することもあります。
生活リズムを整え、安心できる環境づくりも大切です。
- 子どもの歯ぎしりに対して、家でできることはありますか?
-
睡眠環境を整える・就寝前にリラックスするなどが効果的です。
異常が続く場合は歯科でチェックを受けましょう。